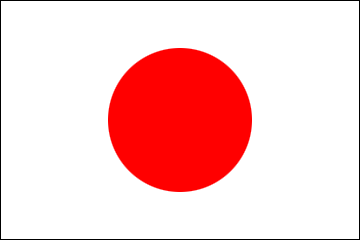証明事務及び戸籍事務手続き
|
|
| (1)手数料のお支払いは現金のみのお取り扱いとなります(支付宝や微信でのお支払いはできません)。 (2)遠方から来館され、持参すべき書類に不安がある方や以下の項目詳細をご覧になりご不明な点がある方は、領事部日本人窓口(021-5257-4766)まで、まずはお電話にてお問い合わせください。せっかくご来館いただいたにもかかわらず、書類が不足している等の理由で当日発行出来ない場合がございます。 (3)本件に関する手続きは、領事部門(上海市延安西路2299号上海世貿大厦13階)にて行っています。本館ではございませんのでご注意ください。【9:00-12:00 / 13:30-17:00(休館日)】 (4)戸籍謄(抄)本は在外公館では発行出来ませんので、必要な方は日本にいる代理人を通じて入手してください。なお、以下の場合は、紙の戸籍謄(抄)本の提出を省略できます(戸籍謄(抄)本の公印証明を発行する場合を除く)。 ※紙の戸籍謄(抄)本の提出を省略できる場合(確認に時間を要することがあります。) (5)在外公館において、婚姻届、離婚届、認知届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、原則として戸籍謄本の提出は不要です。詳細はこちらをご覧ください。また、提出された各種届出の内容が戸籍に反映されるまで、約1ヶ月かかります。反映が完了したという連絡はございませんので、必要に応じて本籍地役場に直接お問い合わせください。 ※証明・戸籍に関するメールでのご相談は、証明・届出専用アドレス(madoguchi@sh.mofa.go.jp)に(1)ご相談内容、(2)電話連絡先を記入の上、ご連絡ください。(@163.com及び@126.comからのメールは受信できませんので、 その他のメールアドレスをご利用ください。) なお、返信に時間がかかる場合がございます。お急ぎの際はお電話ください。また、上記アドレスでは、日本入国査証(ビザ)、中国滞在、邦人援護等のご相談はお答え出来ませんので、予めご承知おきください。 |
| 該当する項目をクリックしてください。 |
|
証明 ※オンライン申請手続きについてはこちら(●:オンライン対象外、■:e-証明対象外) |
|
1 在留証明 2 出生証明 3 独身証明(婚姻要件具備証明)●■ 4 婚姻証明 5 離婚証明 6 帰化証明 7 署名(拇印)証明■ 9 同一人物証明 ●■ 10 警察証明(犯罪経歴証明)●■ ※予約制 |
|
届出(戸籍・国籍) |
|
当館に届出後、戸籍に反映されるまで概ね1ヶ月前後掛かりますが、戸籍に反映された旨を当館からお知らせすることはございませんので、ご自身で本邦市区町村役場にお問い合わせください。 1 出生届 2 婚姻届 4 死亡届 5 離婚届 8 外国国籍喪失届 10 国籍離脱届 11 不受理申立 |
|
|
|
|
|
外国(当館管轄地域内)のどこに住所を有しているか、または有していたかを証明するもの(現在当館管轄地域に居住している場合のみであり、過去の住所のみを証明することはできません。) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)申請人は日本国籍を有している者に限る (2)原則日本に住民登録を有していないこと【注1】 (3)申請人が現地(当館管轄地域である上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、江西省)に既に3ヶ月以上滞在、または3ヶ月以上の滞在が見込まれており、当館に「在留届」が提出されていること【注2】 |
|
|
(1)【必須】本人であることが確認できる文書の原本又は現物(旅券等) (2)【必須】住所を立証できる公的文書(以下(ア)、(イ)のいずれか1つ) (3)【任意】過去の臨時宿泊登記書等(写し可) ※「住所を定めた年月日」に上記(2)に記載されている年月日以前の記載を希望する場合のみ(消費税免税制度を利用する場合は、2年以上前から中国国内に居住していることを証明しなければなりません)。 (4)【任意】現在の本籍地が確認できる紙の戸籍謄(抄)本 (5)申請書兼証明書様式 (現在の住居のみの場合⇒形式1) 形式1で申請される方は、こちらの形式をお使い下さい。→【形式1:Excel/手書き用PDF】(記載例) (現在の住居に加え、過去の住居や同居家族を含める場合⇒形式2)※上記必要書類は同居家族分も必要です。 形式2で申請される方は、こちらの形式をお使い下さい。→【形式2:Excel/手書き用PDF】(記載例)。 ※上記ファイルを使用する際、簡体字に適用するAdobeフォントパックが必要になる場合があります。 |
|
|
|
| 交付日数 | 原則、即日 |
|
|
1通 55元(現金のみ)(但し、恩給、国民年金及び厚生年金等の受給を目的とする場合は手数料を免除(企業年金等は該当しません。)【注7】) |
|
|
(1)形式1(現在の住居の事実を証明)及び形式2(現在の住居の事実に加え、過去の住居の事実または同居家族の住居の事実を証明)があります。また、住所の日本語欄は、日本漢字でご記入いただきますので、事前にお調べください。【参考】日中漢字比較表) |
|
|
|
|
|
いつ、どこで出生したか及び親子関係を証明するもの |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日本人に限らず、元日本人、日本で出生した外国人も申請可能 |
|
|
(1)本人(当事者)であることが確認できる公文書(旅券等) (2)当事者の両親双方の旅券【注1】 (3)出生事実を立証する紙の本邦公文書(日本人の場合は戸籍謄本【注2】、【注3】、元日本人の場合は除籍謄本、日本で出生した外国人の場合は出生届受理証明書等) |
|
|
|
| 交付日数 | 原則、即日 |
|
|
1通 55元(現金のみ) |
|
|
【注1】子の出生証明を申請する場合、提示する戸籍謄本に記載ある親権者1名のみの来館で可。但し、子及び両親の旅券が必要書類となります。 【注2】戸籍謄本の発行日に特段の条件はありません。 【注3】婚姻証明等他の証明と同時に申請する場合、戸籍謄本は1通で可。但し、婚姻証明には出生証明と異なり、発給日より3ヶ月以内の婚姻事実を立証する戸籍謄本が必要となります。 【注4】日本人が中国における帯同目的等での居留許可を取得する際に、中国出入境管理処から求められる「家族関係」を証明する書類として、本証明を使用する場合があります。 |
|
|
|
|
|
申請人が独身であり、かつ、日本国の法令上婚姻可能な年齢に達していることを証明するもの |
|
|
日本人と外国人との婚姻の際に当地官憲当局から求められる場合、不動産手続き等に使用する場合 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)申請人は日本国籍を有している者に限る (2)婚姻手続き目的の場合、原則婚姻予定者の双方が来館 (ただし、婚姻予定相手側の必要書類を持参できる場合は、日本人側のみの来館でも可) |
|
|
<日本人側(申請者本人が準備するもの)> |
|
|
|
| 交付日数 | 原則、即日 |
|
|
1通 55元(現金のみ) |
|
|
|
|
|
現在、誰と、いつから正式に婚姻しているかを証明するもの【注1】 |
|
|
配偶者の呼び寄せ、滞在許可申請、現地における税金控除や家族手当の申請手続、ホテルの同室宿泊等 |
|
|
|
|
|
|
|
|
申請人は日本国籍を有している者に限る |
|
|
(1)本人であることが確認できる公文書(旅券等) |
|
|
|
| 交付日数 | 原則、即日 |
|
|
1通 55元(現金のみ) |
|
|
【注1】解消した婚姻(離婚、死亡)または婚姻歴の証明はできません。 【注2】夫妻のうち1名(日本国籍を有する者)のみの来館で可。但し、夫婦両名の旅券が必要書類となります。 外国人配偶者が代理で申請する際は、日本人配偶者の委任状が必要です。 【注3】出生証明等他の証明と同時に申請する場合、戸籍謄本(婚姻事実と出生事実が記載されたもの)は1通で可。 【注4】日本人が中国における帯同目的等での居留許可を取得する際に、中国出入境管理処から求められる「家族関係」を証明する書類として、本証明を使用する場合があります。 |
|
|
|
|
|
誰といつ正式に離婚しているかを証明するもの |
|
|
滞在資格変更手続、離婚歴の立証または再婚手続等 |
|
|
|
|
|
|
|
|
申請人は日本国籍を有している者に限る |
|
|
(1)本人であることが確認できる公文書(旅券等) |
|
|
|
| 交付日数 | 原則、即日 |
|
|
1通 55元(現金のみ) |
|
|
|
|
|
過去に日本に帰化したことを証明するもの |
|
|
在留許可、在留許可更新、在留資格変更等の申請手続き、不動産手続き等 |
|
|
|
|
|
|
|
|
申請人は日本国籍を有している者に限る |
|
|
(1)本人であることが確認できる公文書(旅券等) |
|
|
|
| 交付日数 | 原則、即日 |
|
|
1通 55元(現金のみ) |
|
|
【注1】正式には帰化証明と称する証明書はなく、戸籍記載事項証明の一種として帰化した事実を証明するものです。 【注2】戸籍謄本に帰化した記載が無い場合は、当館で証明することができません。どの資料に帰化の記載があるかは、本籍地の市区町村にお問い合わせ下さい。 【注3】改製原戸籍や除籍謄本の場合には、現在の本籍地等の記載事項と異なっていても、帰化当時の記載事項が証明書に記載されます。 |
|
|
|
|
|
領事館係員の面前で私文書上の署名および拇印【注1】を行ったことに相違ないことを証明するもの |
|
|
本邦における不動産登記、銀行ローン、自動車名義変更手続等。(基本的に日本の市区町村役場が発行する印鑑証明の代わりとなり、「遺産分割協議書」や「自動車譲渡証明書」 等に申請者署名を求められている場合がこれに該当します。) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)申請人は日本国籍を有している者に限る |
|
|
(1)本人であることが確認できる公文書(旅券等) |
|
|
|
| 交付日数 | 原則、即日 |
|
|
1通 80元(現金のみ) |
|
|
形式1(←貼付型サンプル:本証明の提出先から署名(及び拇印)を求められている書類がある場合)と 形式2(←単独型サンプル:本証明の提出先から署名(及び拇印)を求められている書類がない場合)があります。 【注1】署名のみの証明は可能ですが、拇印のみの証明は出来ません。 【注2】日本に住民登録をしている(住民票がある)場合、提出先が印鑑証明(住民票がある場合は、その市区町村役場で印鑑証明の入手が可能)ではなく、本証明を要求していることを示して頂く必要があります。 【注3】署名及び拇印は、領事館係員の面前で行って頂きますので、事前には行わないでください。 |
|
|
(公文書上の印章(署名)の証明) |
|
|
我が国の官公署(国、地方公共団体または裁判所)または独立行政法人、特殊法人、学校が発行した文書の発行者の印章(職印または機関印または署名)が真正である旨の証明 |
|
|
現地官憲等から諸手続きに必要として提出が求められた場合 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)日本人に限らず、元日本人等の外国人(例:日本の大学を卒業した中国人)も申請可 |
|
|
|
|
|
|
| 交付日数 | 原則、即日(※印影の確認に時間を要する場合など、後日交付(1~3開館日程度)となる場合があります。) |
|
|
(1)官公署に係るもの 1通 215元(現金のみ) (2)その他のもの 1通 80元(現金のみ) |
|
|
【注1】以下のものは証明できません。 (1)外務省及び在外公館が発行した公文書の公印の証明 【注2】 (2)犯罪経歴証明書を中国行政機関に提出する場合は、日本国外務省においてアポスティーユを取得することが一般的ですが、その他の方法をご希望される方は当館領事部にご連絡ください。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
日本での犯罪経歴(無犯罪の証明)を証明するもの |
|
|
米国、カナダ等外国への永住申請、中国の就業許可・永住権申請等の際に関係当局より要求された場合に使用する。 |
|
|
|
|
|
人定事項(氏名、生年月日)は日本語及び英語、本邦における犯罪歴の有無は日、英語併記 |
|
|
(1)日本国内に居住したことがあること |
|
|
(1)有効期限内の旅券 |
|
|
|
|
|
|
|
|
【予約制】 o その他の国も提出先(我が国の警察証明を要求した機関)によっては、警察証明(犯罪経歴証明)に対して、外務本省における公印確認及び駐日本外国公館の認証(領事認証)を要求する場合がありますので、事前に提出先(日本国の警察証明を要求した機関)にご確認ください。 o 使用目的によっては、(1)申請者が提出先(外国の関係機関等)より本証明書の提出を求められていることが確認できる文書(申請人宛レターまたは電子メール)及び同和訳文に加え、(2)提出先国の関連法規(提出先が如何なる法規を根拠に申請人に対し本証明書の提出を求めているかが確認できる文書)の写し及び同和訳文が必要となる場合がありますので、事前に当館宛にお問い合わせください。(中国・アメリカ・カナダ・オーストラリア永住や中国での就業目的の場合は、原則疎明文書不要。)【注1】 o 申請人が日本国籍の場合は不要です。【注2】 |
|
|
「子の出生に関する手続き」(リンク)をご参照ください。 |
|
|
(1)届出人の身分証明書(旅券等) ※¹ 漢字表記はすべて日本漢字でご記入いただきますので、各自で事前にお調べください。 【参考】日中漢字比較表 ※² 人名に使用できる漢字については、こちらからご確認ください。 (3)子の出生医学証明書1通(通常病院で発行されるもの)【注2】 |
|
|
原則子の親権者1名のみの来館で可(子の来館は不要)【注3】 |
|
期限 |
出生後3ヶ月以内 |
|
|
(1)中国で生まれた子については、日本人同士の父母の子の場合を除き、出生届とともに日本国籍を留保する意思を表示して、出生日を含め3ヶ月以内に届出をしなければ、出生の時にさかのぼって日本国籍が喪失されますのでご注意ください(戸籍法第49条及び第104条、国籍法第12条)。 (2)当館ではなく、直接日本の市区町村役場に届出る場合、出生医学証明書の原本は必ず同じ状態(副票を切り取られないよう)で返却してもらう必要があります(副票を切り取られると中国での居留許可申請が出来なくなる恐れがあります)。 【注1】 届書の署名以外の部分は、コピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したもので可。 【注2】 当館にてコピー後返却します。 【注3】 婚姻関係のない相手との間の子の出生届の場合、届出人(親権者)が母のみとなります。但し、母が外国人の場合、父が出生前に胎児認知を行っていなければ届出はできません。 |
|
|
|
|
|
<日本人と中国人> 「中国人と結婚する際の手続き」(リンク)をご参照ください。 (1)旅券(日本人)、身分証明書(中国人) ※漢字表記はすべて日本漢字でご記入いただきますので、各自で事前にお調べください。 【参考】日中漢字比較表 (3)婚姻公証書2通(1通は原本、2通目は写し可)【注2】
(1)双方の旅券 (2)婚姻届(証人欄の記載も必要ですので、こちらを印刷の上、お使いください。当館でも入手可)2通【注1】、【注4】 ※漢字表記はすべて日本漢字でご記入いただきますので、各自で事前にお調べください。 【参考】日中漢字比較表
※当館では受理出来ません。日本人が中国人以外の外国人と結婚する場合に、中国機関では結婚登記を受理しないため、日本方式(日本の市町村役場に直接届出)又は結婚相手方の国の方式で結婚手続きを行う必要があります。 |
|
|
|
|
期限 |
|
|
|
【注1】 届書の署名以外の部分は、コピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したもので可。 【注2】 中国人配偶者の地元公証処で発行されるものです。 【注3】 和訳文には、作成年月日、和訳者の署名及び押印が必要です。(中国の公証処では日本語仮訳対応が可能な場合もあります。) 【注4】 証人(2名)は婚姻届(2通)の所定欄に署名、押印する必要があるため、届出人とともに来館するか、婚姻届を事前に入手し、署名、押印済みの婚姻届を持参する必要あります。なお、証人は成年に限ります。また、全通同一の人が行う必要があります。 【注5】 日本の方式以外で婚姻が成立した日から3ヶ月を超えて提出する場合は、婚姻届遅延理由書(様式は任意です。)を2通提出する必要があります。 |
|
|
|
|
|
<既に出生した子の認知>【注1】 (1)届出人(父)の旅券 (2)認知届 2通【注2】 (当館でも入手できます。) ※記載例はこちら ※漢字表記はすべて日本漢字でご記入いただきますので、各自で事前にお調べください。 【参考】日中漢字比較表 <胎児認知>【注6】 (1)届出人(父)の旅券 (2)認知届2通 (当館でも入手できます。) ※記載例はこちら ※漢字表記はすべて日本漢字でご記入いただきますので、各自で事前にお調べください。 【参考】日中漢字比較表 |
|
|
|
|
期限 |
|
|
|
【注1】日本国籍を取得するためには、別途国籍取得に関する手続きが必要となります(認知届の提出だけで日本国籍を取得できません。)。 【注2】 届書の署名以外の部分は、コピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したもので可。 【注3】当館にてコピー後、返却します。 【注4】兄弟等で同時に行う場合で、双方に共通するものは原本1通。2通目以降は写し可 【注5】2015年より民政局にて「婚姻記録証明」が交付されなくなりました。婚姻履歴、場所により用意できる資料が異なりますので当館までご相談下さい。 【注6】日本国籍を取得するためには、出生から3ヶ月以内に出生届を提出する必要があります。 【注7】外国人父が日本人母の子を認知する場合の届出は受理出来ません。 |
|
|
「中国で死亡された場合の手続き」(リンク)をご参照ください。 |
|
|
(1)届出人の身分証明書(旅券) ※漢字表記はすべて日本漢字でご記入いただきますので、各自で事前にお調べください。 【参考】日中漢字比較表 (3)死亡者の氏名、死亡場所及び死亡年月日時分が記載されている「死亡診断書」(死亡者を診察した医師が作成するもの)または「死体検案書」(死亡者を診察しなかった医師が死亡後に死体を検案して作成するもの)【注3】 (4)上記(3)の和訳文2通 |
|
|
(届出義務者) 1位:同居の家族 2位:その他の同居者 3位:家主、地主、または管理人 |
|
期限 |
|
|
|
【注1】 届書の署名以外の部分は、コピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したもので可。 【注2】 死亡者の本籍及び戸籍の筆頭者を死亡届に記載できるよう、事前に確認してください。 【注3】死亡した病院または立ち会った医師の発給、作成した証明書、または政府機関発給の死亡登録証明書がこれに該当します。 但し、やむを得ない事由により「死亡診断書」または「死体検案書」が提出できない場合、これらを入手できない理由を記載するとともに、別途死亡の事実を証する書面をもってこれに代えることができる場合があります。但し、当該書面として認めることができるかの判断について、審査に時間を要します。 |
|
|
|
|
|
<日本人と中国人> (1)届出人の旅券(日本人のみ) (2)離婚届(当館でも入手できます。)2通(証人不要)【注1】 ※漢字表記はすべて日本漢字でご記入いただきますので、各自で事前にお調べください。 【参考】日中漢字比較表 (3)離婚公証書2通【注2】(1通は原本、2通目写し可) <日本人同士>【注4】 (1)双方の旅券 (2)離婚届(当館でも入手できます。)2通【注1】、【注5】 ※漢字表記はすべて日本漢字でご記入いただきますので、各自で事前にお調べください。 【参考】日中漢字比較表 <日本人と中国人以外の外国人> (1)届出人の旅券(日本人のみ) (2)離婚届(当館でも入手できます。)2通【注1】(証人不要) ※漢字表記はすべて日本漢字でご記入いただきますので、各自で事前にお調べください。 【参考】日中漢字比較表 (3)公的機関が発行した離婚を証する書面 2通(1通は原本、2通目写し可) |
|
|
|
|
期限 |
|
|
|
【注1】 届書の署名以外の部分は、コピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したもので可。 【注2】 中国人元配偶者の地元公証処で発行されるものです。 【注3】 和訳文には、作成年月日、和訳者の署名及び押印が必要です。(中国の公証処では日本語仮訳対応が可能な場合もあります。) 【注4】 <日本人同士>であっても、既に中国の方式において離婚している場合は、<日本人と中国人>と同様に離婚公証書及びその和訳文(各2通)が必要です。なお、その場合は証人の署名、押印は不要です。 【注5】 証人(2名)は、離婚届(2通)の所定欄に署名、押印する必要があるため、届出人とともに来館するか、離婚届を事前に入手し、署名、押印済みの離婚届を持参する必要があります。なお、証人は成人に限ります。また全通同じ人が行う必要があります。 【注6】 <日本人同士>であっても、既に中国の方式において離婚している場合は、当事者双方のうちどちらか一方のみで可【注7】。 【注7】日本国籍を有する未成年の子がいるときは、それぞれの子について夫と妻のどちらが親権を行うかを決め、子の氏名を本届けに書く必要があります。本届出に上記(未成年の子の氏名)を記載する場合は、夫と妻両者の署名と捺印(拇印)が必要となります。 【注8】 離婚成立の日から3ヶ月を越えて提出する場合は離婚届遅延理由書を2通提出する必要があります(任意様式)。 |
|
|
|
|
|
(1)届出人の旅券 (2)氏のフリガナの届 名のフリガナの届(当館でも入手できます。)2通【注1】 ※漢字表記はすべて日本漢字でご記入いただきますので、各自で事前にお調べください。 【参考】日中漢字比較表 |
|
|
|
|
期限 |
|
|
|
【注1】 届書の署名以外の部分は、コピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したもので可。マイナポータルからも届出ができます。 【注2】 未成年者の場合は、法定代理人である親権者。15歳以上の未成年者の場合は、本人も届出することができます。 【注3】 期限までに届出がされない場合、市区町村がもつ情報をもとに、自動的に戸籍にフリガナが記載されます。ただし、長期間の海外滞在等、日本の市区町村に住民情報がない場合は、戸籍にフリガナは記載されません。この場合には、2026年5月26日以降であっても氏名のフリガナを記載する申出をすることができます。 |
|
|
|
|
|
(1)届出人の身分証明書(旅券等) (2)国籍選択届 2通 【注1】 ※当館でも入手できます。※記載例はこちら ※漢字表記はすべて日本漢字でご記入いただきますので、各自で事前にお調べください。 【参考】日中漢字比較表 |
|
|
当該重国籍者が15歳以上である時は本人、15歳未満の時はその法定代理人(父母両者等)【注2】
|
|
期限 |
18歳に達するまでに重国籍となった者は、20歳まで【注3】。 |
|
|
【注1】 届書の署名以外の部分は、コピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したもので可。 【注2】法定代理人が外国人であっても届出可能(ただし、父母両者が法定代理人の場合、父母両者の来館が必要)。 【注3】中国人との間に産まれたこと等により重国籍になった方は、20歳を待たずに届出可能です。 【その他】 (1)本届出を行った場合、戸籍謄本には、【国籍選択の宣言日】の記載が追加されます。 |
|
|
|
|
|
(1)外国国籍喪失をした者(当事者)及び届出人の身分証明書(旅券等) ※漢字表記はすべて日本漢字でご記入いただきますので、各自で事前にお調べください。 【参考】日中漢字比較表 |
|
|
当該重国籍者が15歳以上である時は本人、15歳未満の時はその法定代理人(父母両者等)【注2】
|
|
期限 |
18歳に達するまでに重国籍となった者は、20歳まで【注3】。
|
|
|
【注1】 届書の署名以外の部分は、コピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したもので可。 【注2】法定代理人が外国人であっても届出可能(父母両者が法定代理人の場合、父母両者の来館が必要)。 【注3】中国人との間に産まれたこと等により重国籍になった方は、20歳を待たずに届出可能です。 【注4】原本が1通しか発行されないものに関しては、当館にて写しを取った上で原本はご返却します。 【その他】 (1)本届出が適法な届出と認められた場合には、戸籍謄本に、外国籍を喪失した旨の記載がなされます。 |
|
|
|
|
|
(1)自己の志望により新たに外国国籍を取得または外国国籍を選択した者(以下当該人)及び届出人の身分証明書(旅券等) 【参考】日中漢字比較表 |
|
|
当該人(または配偶者、四親等内の親族)【注3】
|
|
期限 |
国籍喪失の事実を知った日から1ヶ月以内。 (ただし、国籍喪失の事実を知った日に日本国外にいた(いる)場合は、3ヶ月以内) |
|
|
【注1】 届書の署名以外の部分は、コピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したもので可。 【注2】原本が1通しか発行されないものに関しては、当館にて写しをとった上でご返却します。 【注3】国籍喪失届の届出人署名押印欄は、当該人が届出人の場合のみご記入ください。また、当該人以外が届出人となる場合は、その下の「届出人(国籍を喪失した人以外の人が届けるとき)」欄に署名・押印をしてください。 【その他】 (2)本届出の際は、当館にて当該人の日本国旅券の失効処理を行いますので、必ず旅券原本をご持参ください。 |
|
|
|
|
|
(1)国籍を離脱しようとする者(以下、当該重国籍者)及び届出人の身分証明書(旅券等) ※漢字表記はすべて日本漢字でご記入いただきますので、各自で事前にお調べください。 【参考】日中漢字比較表 (5)中国等外国官公署が発行する当該重国籍者の住所公証書2通(1通は原本、2通目写し可) |
|
|
当該重国籍者が15歳以上である時は本人、15歳未満の時はその法定代理人(父母両者等)【注2】
|
|
期限 |
随時。 |
|
|
【注1】届書の署名以外の部分は、コピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したもので可。 【注2】法定代理人が外国人であっても届出可能(父母両者が法定代理人の場合、父母両者の来館が必要)。 【その他】 (1)本届出が適法な届出と認められた場合は、当該重国籍者の本籍地役場へ戸籍削除の手続きがなされますので、国籍喪失届は不要です。 (2)本届出が適法な届出と認められた場合は、日本国法務省より発行された「国籍離脱通知書」が交付されます。交付を受ける前に、当館にて当該重国籍者の日本国旅券の失効処理を行いますので、必ず旅券原本をご持参ください。 |
| 11 | 不受理申立 |
| 概要 | 自分の知らない間に自身の意思に基づかない届書が提出され、戸籍に真実でない記載がされるのを防止するための申出です。(戸籍法第27条の2第3項) 対象となる届書は、届出によって身分行為(身分の取得や変動)の効力が生じる「創設的届出」となる婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届となります。 ただし、外国法により成立した、又は、裁判により確定したことによる「報告的届出」は、この不受理申出をしていても受理されます。 |
|
|
(1)不受理申出書 2通(在外公館の領事窓口にあります。) (2)申出人のご本人確認書類(旅券等) (3)15歳未満の者について申出を行う場合は、法定代理人であることを証明する書類 原本1通・写し1通(戸籍謄本等) |
| 申出人 | 不受理申出をする本人(本人が15歳未満の場合は法定代理人)で、日本国籍の方。【注】 ※自身が届出人になる届書についてのみ申出可能。 |
|
届出
期限
|
不受理申出の有効期間は、申出人本人が窓口に出頭して対象の届出をするか、不受理申出の「取下げ」をしない限り、無期限です。 |
| 備考 | 【注】外国籍の方が申出する場合 外国籍の方も日本人を相手方とする不受理申出をすることができますが、在外公館では、外国籍の方からの不受理申出を受け付けることはできません。(在外公館で申出できるのは、日本人のみとなります。) 従いまして、外国籍の方は、原則として、日本の市区町村役場の窓口に出頭して不受理申出を行う必要がありますが、疾病その他やむを得ない事由により自ら出頭できない場合は、(1)申出をする旨、(2)申出の年月日、(3)申出する者の氏名、出生年月日、住所及び戸籍の表示等を記載した公正証書を提出する等で当該申出をする者が本人であることを明らかにすること(戸籍法施行規則第53条の4第4項)により、書面の送付により申出ができる場合もありますので、申出予定の市区町村役場の担当部署に適宜問い合わせてください。 |
<在上海日本国総領事館領事部連絡先>
申請場所:在上海日本国総領事館別館領事部門(上海市延安西路2299号上海世貿大厦13階)
開館時間:9:00-12:00 / 13:30-17:00(休館日こちらでご確認ください。)
電話:021-5257-4766(日本人窓口)