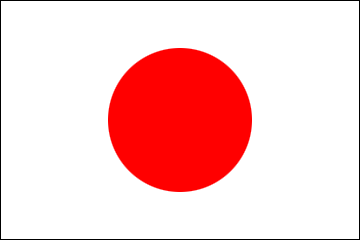日中音楽の架け橋~和楽器の音色を楽しもう~を開催しました

一曲目の演奏は箏による「さくらさくら」です。日本の箏は奈良時代(約1300年前)に中国から伝わりました。桐でできており、中国の古箏と違って弦は13本です。右手の3本の指にはめた爪ではじいて演奏します。

続いて尺八独奏で「巣鶴鈴慕」、尺八と箏で「春の海」が合奏されました。尺八は中国あるいは朝鮮半島を経由して日本に伝わりました。色々な長さの尺八がありますが、最も一般的なものが一尺八寸(約54.5cm)であることから、「尺八」と呼ばれています。楽器の解説を担当した音楽研究家の釣谷真弓先生は、尺八は竹で作られているが、パンダが食べる竹とは違うと話し、会場の笑いを誘いました。

4曲目は和楽器合奏による「八千代獅子編曲」。八千代(千葉県)の獅子舞をモチーフにしており、めでたい場面で演奏されることの多い曲です。

三味線は江戸時代、物語の伴奏として使われ発展しました。太さの異なる3本の弦をバチではじいて音を出します。

5曲目は琵琶による「祇園精舎」。日本の琵琶は中国の琵琶と異なります。日本の琵琶は最初は雅楽に使われ、時代が下ると読経の伴奏に使われるようになりました。銀杏の葉のような形をしたバチを使って演奏します。

6、7曲目は尺八による「風の色」と「郷音」。

最後の曲として、日中両国の平和と友好を記念し、高橋久美子氏が作曲した「音の架け橋」が合奏されました。この楽曲は、和楽器だけでなく、中国の民族楽器でも演奏が可能で、まさに日中両国の音の架け橋となるべく創られた曲です。

今回、こうべ邦楽ワークショップから当館に対し箏が寄贈されることになり、演奏終了後に寄贈式を行いました。こうべ邦楽ワークショップ代表の名村茂代先生から箏2面の目録、音楽研究家の釣谷真弓先生から著書2冊が竹中惠一副総領事に手渡されました。

続いて、竹中副総領事が挨拶し、こうべ邦楽ワークショップに対し、当館への箏の寄贈、並びに、長年にわたる文化交流を通じた日中友好親善への貢献に、感謝と敬意を表しました。
最後に、参加者が待ちに待った楽器体験が行われました。参加者は箏、三味線、尺八、琵琶など、自分の体験したい和楽器の前に並んで順番に体験しました。

箏の体験


三味線の体験

琵琶の体験


尺八の体験

こうべ邦楽ワークショップの先生方、そして熱心な参加者の皆様ありがとうございました。当館では今後も様々な日本文化活動を開催していきますので、どうぞご期待ください。